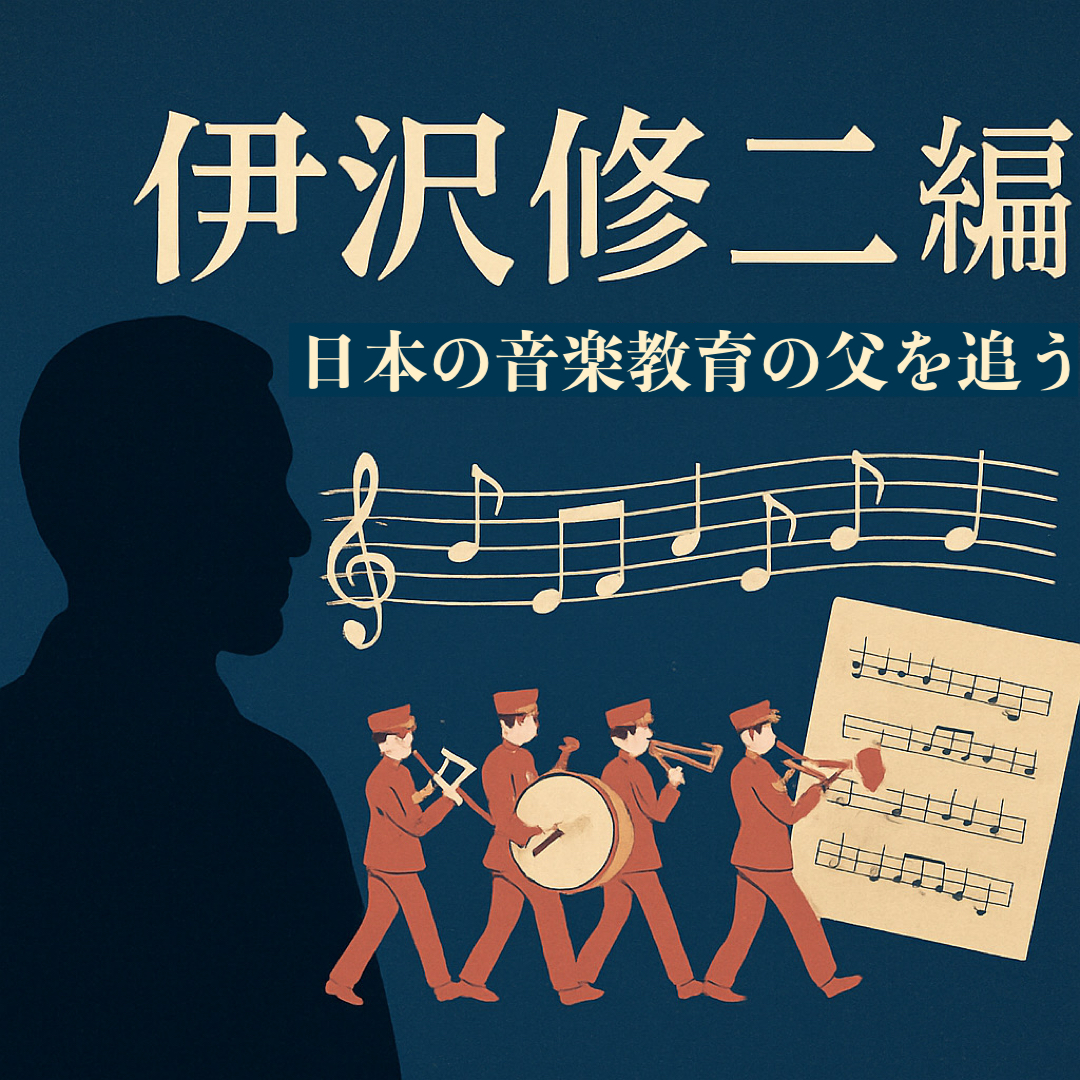🎵 伊沢修二って、誰?
伊沢修二と言えば
「あー、あの政治家の?」
「あー、昔お札に載ってたよねー」
とか。思ってしまいそうな名前だけど。
…思った人何人かいますよね?
でも政治家でもないし、お札に載ってる人でもありません。
📘 目次
🎤 伊沢修二は、「日本の音楽教育の父」
伊沢修二は、「日本の音楽教育の父」と言われる人です。
彼は日本の学校に、音楽を制度として導入しました。
伊沢修二がいなければ、日本の学校に音楽の授業なんてなかったかもしれません。
「…余計なことを…」とか思う人も、少なからずいそうですよね。
🎧 音楽の授業、好きだった?
音楽は好きでも、学校の授業は嫌いだったって人もいるかと思います。
- 「人前で歌わされるのが嫌だった」
- 「苦手な楽器をさせられるのが嫌だった」
- 「そもそも何のために必要なのかがわからない」
他にも色々とあるんじゃないでしょうか。
勿論、大好きだったと言う人もいるでしょう。
でもまぁ、別に学校の授業でやらなくても。
音楽はやりたい人が個人で習いに行けばいいし、
また音楽は評価されるものじゃなくて自由にやるものだし。
嫌だと思う子に無理にやらせなくてもいいんじゃね?
って、思う人も多いんじゃないでしょうか。
💡 どうして学校に音楽を?
どうして伊沢修二は、わざわざ音楽を学校教育に取り入れようとしたのか。
それは彼の生きた時代が大きく関わっていました。
🕰 江戸末期から明治へ——激動の時代
江戸末期から明治にかけて。
激動の時代を駆け抜けた伊沢修二。
その中で彼が作り上げた音楽教育と唱歌の誕生秘話。
彼の人生を追いかけながら、彼が音楽教育に何を見たのか。
学校制度に音楽を導入することに、どんな意味があったのか。
それをみなさんと一緒に見ていきたいと思います。