📚 目次
⛪ 一神教ってなに?
まず、「キリスト教は一神教」であること。
これはとても大事な概念です。
日本の神道やギリシャ神話のような「多神教」とは異なり、キリスト教では人々が唯一絶対の神に祈りを捧げます。
この唯一の神を信じることで、信仰を共有し、共同体としての結びつきが強まる――これが一神教の持つ大切な特徴のひとつなんですね。
🎵 聖歌の混乱時代へ
ところが、当時の典礼や聖務日課に使われる聖歌は、地域によってバラバラでした。
なんせ当時は YouTube も Spotify もないし、CDやカセットテープもありません。
いや、そもそも「楽譜」という概念すらなかったのです。
つまり、正確な音を残す術がまだ無かったんですね。
一応、修道士たちが「ネウマ」と呼ばれるメモのような記号は書き残していました。
でもその役割はあくまで補助的。
低い位置に「点」、高い位置に「点」を書いて、
「この辺で音が上がるんだってさ〜」
「ほぉ〜ん」
くらいのゆるさだったのです。
その状況で修道士たちは、何百曲〜1000曲以上を、先輩からの口伝、つまり耳コピで覚えてたんです。
そんなだから、例えば派手好きなやつが
「ここもっと音多かった気がする〜」
とか。
声に自信のある奴が
「ここもっとながーい音だった気がする〜」
とか。
ちょっと物忘れの激しい人が
「正直この部分覚えてないけどまあ適当に〜」
とか。
そんな事が簡単に起きてしまうんですね。
そうなると
「皆が同じ神を讃えるはずの歌が、土地ごとに全然違う」
……なんてことも起きるわけです。
違う土地に行った修道士が
- 「あれ?ここの音そんな感じでした?」
- 「え?ご存知ない?正統な歌い方はこうなんですよ?」
- 「いやいやwあなたが何か勘違いされているのでは?」
- 「いやいやあなたが…」
- 「いやいやあんたが…」
- 「いやおまえが…」
- 「いやきさま…」
なんてことも起きるわけです。
🛠 なぜ統一しようとしたの?
そんな一体感の無さを憂いた人たちが、一旦各地の聖歌を集めて。
無駄な派手さを削ったり、共通する部分を残したりして編纂したんです。
でもいくらそれを「正統だ!」と主張したところで
「いやうちが…」「いやこちらが…」ってなるに決まってるので。
「いや、あのグレゴリウスさんが〝これやで〟って言うてはりましてん」
と言ってしまえば
「…。そっスか…。ええメロディや思てましてん」
と。
大方こんな感じだったんじゃないでしょうか。

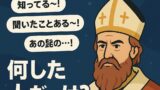
コメント