📚 目次
🛡️ フランク王国とグレゴリオ聖歌の広まり
そして、グレゴリウスの時代から約200年後。
西ローマを制圧してフランク王国を築いたゲルマン民族の王様「カール大帝(トランプの王様!)」が、支配をスムーズに進めるため、ローマで編纂されていた聖歌を自国でも普及させようとしました。
その時も「これこそ正統なもの」とする為に
「あのグレゴリウスさんが編纂した聖歌なんやで」と。権威付けをしたのです。
こうしてこの聖歌は「グレゴリオ聖歌」と呼ばれるようになり、グレゴリウスの功績として語り継がれていきました。
🎼「8つのモード」の発見とグレゴリオ旋法
しかしカール大帝の時代でも、まだ修道士たちは数百曲の聖歌を耳コピするのが基本でした。
この作業は覚える方も大変だけど、正確に教える方も大変。
「これ何っとかなれへんのかなぁ〜」と悩む声も。
そんな中、この時代の理論家たちが聖歌を分析してみたところ、
- 「あれ?これって8つくらいのパターンに分類出来るんじゃない?」
- 「分類できたら教えやすくない?」
という事に気づきます。
そうして発見・整理されたのが「8つのモード(音階)」。
これが後に「グレゴリオ旋法」と呼ばれるようになる、教会旋法(チャーチモード)の体系です。
👑 グレゴリウスの伝説的な功績
いやー。
すごい。
生前に残した功績が死後、高い評価を得るなんてのは聞いたことありますが…
グレゴリウスの場合、
生前は音楽について何もせず。
死後に当時の聖歌を編纂し、まとめ上げ、旋法まで発見し、
音楽の世界に物凄い功績を残し、高い評価を得たと…。
🎤…いや、おる?
そんなやつおる!!??
でもそれがグレゴリウス1世。
「大教皇」と呼ばれたアルティメットな男!!✨

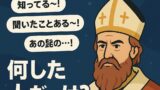
コメント